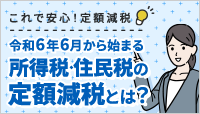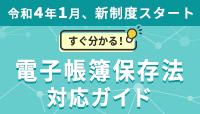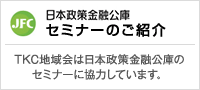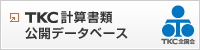「人工知能(AI)」といえば2016年を象徴するバズワードだ。自動運転の進化、ヒト型対話ロボットの活躍、囲碁のプロ棋士との対戦など話題に事欠かない。『人工知能が変える仕事の未来』(日本経済新聞出版社)を上梓した野村直之氏がAIの可能性を語る。
- プロフィール
- のむら・なおゆき 1962年生まれ。1984年東京大学工学部卒業、2002年理学博士号取得(九州大学)。NECC&C研究所、ジャストシステム、法政大学、リコー勤務をへて法政大学大学院客員教授。2005年メタデータ株式会社を創業。ビッグデータ分析、ソーシャル活用、各種人工知能応用ソリューションを提供。この間、米マサチューセッツ工科大学(MIT)では人工知能の父といわれるマービン・ミンスキーと一時期同室。ディープラーニングを支えるイメージネットの基礎となった、ワードネットの活用研究に携わる。
──昨今のAIを取り巻く状況をどのようにみていますか。
野村 かつて1950~60年代と80年代の2度にわたり、AIブームがわき起こりました。近年の状況は第3次AIブームといえるでしょう。将来的にAIが人間から仕事を奪ったり、2045年までに人間の能力を上回るいわゆるシンギュラリティが訪れるといった、危機感をあおる言説が目につきます。
ガートナージャパンが2016年10月5日に発表した「日本におけるハイプ・サイクル:2016年」によると、サイクルの頂点に位置しているのがAIにほかなりません(『戦略経営者』2017年1月号21頁・図表1参照)。市場に登場した新たな技術はまず過熱気味にもてはやされ、熱狂が冷め、意義や役割が理解された後に市場が確立するという過程をたどります。つまりAI市場が過熱状態にあるいま、AIの搭載をうたう製品やサービスの性能は慎重に見極める必要があるということです。
──確かにAIイコール最先端というイメージが流布しています。
野村 実態は玉石混交で、そもそもAI(Artificial Intelligence)の定義すら研究者によってまちまちです。私なりには知能とは「未知の問題、初めて接した状況に対処し問題を解決できる能力」であると解釈しています。その意味において現状ではAIは存在していないし、つくられる見通しも立っていない。それでは話が進まないので、AIを少しゆるく「知的なふるまいをするソフトウエア」と定義してみます。
AIには数多くの種類がありますが、「強弱」「汎用性」「知識・データ量」の3軸で分類できます(同・図表2参照)。強いAIとは、あたかも人間と同じように自ら考え行動できるAIを指し、一方、人間の能力を補完する役割をもつAIを弱いAIと呼びます。二つめの軸の汎用性とは、未知の事態にある程度対応できる学習能力の有無です。
IBMの「ワトソン」というコンピューターは、クイズ王をしのぐほどあらゆるジャンルに関する大量の知識を持っていて、一見汎用的のように思えます。しかし、専門ごとに知識を獲得するアルゴリズムが微妙に異なっており、専用AIの集合体と見なした方が適切でしょう。ワトソンはクイズ番組で出題された膨大なパターンを覚えこませることで正答率を上げていきました。とはいえ、苦手なジャンルもあり、人間が日常生活やさまざまな経験を通して身につける「知能」が問われる設問は苦手です。
──例えば?
野村 試験問題として良問中の良問としていつも挙げているのが、私が1980年に東京大学理科Ⅰ類を受験したときに出題された物理の問題です。どんな問題文だったかというと「白熱電球をつけた電気スタンドの電源ケーブルをコンセントから抜いたとき、瞬時に真っ暗にならず時間をかけて暗くなるが、なぜそうなるのか理由を証明せよ」というものでした。
熱力学の法則と電磁気学の法則をもとにいくつかの方程式を組み合わせると解けるのですが、ただ単に数式を解く問題よりもはるかにむずかしい。私も当時なぜ解くことができたのか、今となっては明確に説明できません。森羅万象の常識、経験に裏打ちされた本物の知能が備わっていないと解答するのは不可能です。東大合格を目指していた「東ロボくん」プロジェクトが進路変更せざるを得なくなったのも、こうした理由からでしょう。
最近の話題でいえばさきの米大統領選で、あるAIはヒラリー・クリントン候補の勝利を予測していました。しかし、学者のエマニュエル・トッド氏や経営コンサルタントの宋文州氏など、ドナルド・トランプ氏当選を予測していた人がいたのも確かです。彼らは自身の頭で論理的にものごとを考え、的確な予測をしました。ヒラリー氏有利とする分析やコメントが世の中にあふれかえれば、AIはそれを学習するだけなのです。
深層学習がAIの嚆矢に
──AIが進化すれば東大の難問も解けるようになるのでは。
野村 まず無理でしょうね。AIはいつ人間の能力をこえられるかということを議論する人がいますが、この命題自体、あまり意味がないと思っています。例えば6メートルの高さの木になっている実を5メートルの棒を使えばかんたんに落とせます。世の中にあるあらゆる道具は、専門性においてすでに人間の能力を上回っているのです。
──ではAIの得意とする領域というと?
野村 大量のデジタル画像の中から特徴を抽出し、識別するディープラーニング(深層学習)という技術があります。当社はディープラーニングをベースにした「このネコなにネコ?」というアプリケーションを販売しています。これは入力したネコの種別を世界の70種類のネコの中から一瞬のうちに判別するウェブアプリで、95%をこえる精度があります。商品企画、市場調査からデータ収集、検証作業を8日間で行い、販売開始にこぎつけました。ディープラーニングは監視業務や病気の判定など、幅広く役立てられる可能性を秘めています。
ある損害保険会社では、契約者であるタクシー会社の運転手約1000人が危険な運転をしていないか、一日中ビデオを見てチェックしている社員がいるそうです。500時間のうち危険な運転をしているのが100秒間あったとして、危険運転とAIが指摘できたとします。人間はその100秒間だけを念のためチェックすればよく、生産性は格段に上がります。
──AIなら疲労の心配もいりません。
野村 AI活用によりメリットを享受できるのは単純作業にとどまりません。日ごろ営業担当者が営業日報をつけている企業は多いと思いますが、営業日報に書かれた内容を解析し、受注・失注との相関関係を分析することも可能です。もっとも、セールスの現場で相手と交渉し、妥協点を探りながら説得するといった芸当はAIにはできませんが。
身近なところでは、ホテルの予約受付システムなどで「イールドマネジメント」というソフトウエアが活用されています。宿泊予約の問い合わせを受けたとき、話し方やリクエスト内容から宿泊単価レートを判断。顧客プロフィルや過去の宿泊履歴をもとに確率計算を行い、高レートの上客で空室を埋めるのです。もし目下の客の宿泊予約を断ったとしてもその後、長く宿泊してくれる客が現れる確率が高ければ、端末の画面上にその旨のメッセージが表示されます。
こうしたソフトを導入すれば、人間が経験やカンで宿泊予約を受け付けるよりも、利益は確実に上がるはずです。法的な問題がクリアできたとして、顔認証でリピート客かどうかチェックするといった機能も付加されれば、AIと呼ぶにさらにふさわしくなります。
マッチング性能に強み
──データ量が増えるほど精度は高まると。
野村 大量のデータ同士をマッチングするのはAIの得意とする分野です。政府は働き方改革を進めるため生産性の向上を目標に掲げていますが、カギとなるのは社員がいかに前向きに業務に取り組めるか。社員の希望職種、適性、家庭環境などを考慮して適材適所の人材を配置するのはむずかしいものです。人間と仕事を結びつける人事においても、AIの活用は大いに期待できます。人材派遣会社では多数の登録者と仕事の最適なマッチングを図るといった用途も生まれるでしょう。
ファイナンス(Finance)とテクノロジー(Technology)をかけあわせた「フィンテック(Fintech)」という用語を最近よく聞きます。金融業界は勘定系のオンラインシステムを早い時期から構築し、IT化に力を入れてきました。米国では個人間融資の審査代行をし迅速に融資を実行したり、決済送金手数料を低価格に抑えるITベンチャーが次々と登場しています。なにも金融業界にかぎらず、マーケティング・営業分野では「Marchetech」、人事・採用分野は「HRTech」、法務分野は「LegalTech」と呼ばれ、X+Technology=X-techの動きは広がっていくでしょう。
──2020年の東京五輪開催に向けて、国や東京都は東京を先端技術のショーケース化したい意向のようですが。
野村 よく話題にのぼるのが自動運転ですね。自動運転先進国の米国では、地方のハイウエーを10時間近く運転しても対向車とまったくすれ違わないといった環境を前提に開発が進められており、日本と事情がまったく異なります。トラックドライバーが失業する危機感を抱くのもうなずけます。
翻って日本ですが、運転代行サービスや一定のルートを走行する巡回車を皮切りに自動運転が実用化されていく可能性があると思います。自動運転で事故を起こしたときの責任など法整備を整えておく必要もあるでしょう。自動運転中、子どもが目の前に飛び出してきて急ブレーキを踏んでも間に合わないとき、AIはどんな判断をくだすのか。AIが進化して周囲の人の年齢や家族構成をもとに損害賠償額を計算して、一番安く済みそうなところにハンドルを切るといった動作を行うようになれば恐ろしい話ですが。
疑問がひらめきを生む
──経営者はAIにどう向き合うべきでしょうか。
野村 AIの性能を慎重に判断する必要はありますが、おそれずに活用していきましょうと言いたいですね。普通のプログラミングを用いて開発しているにもかかわらず、AIを魔法の言葉のように利用し製品を販売する企業が増えてきています。「人工知能により○○します」あるいは「人工知能が良い結果をもたらします」といった、人工知能をあまりにも前面に押し出している製品は疑ってみたほうがいいかもしれません。世の中の人工知能には数千種類の方法があり、定義もまちまちだからです。
一方「ディープラーニングだけで十分トレーニングを行え、オプションで精度を高められます」とか「当社の製品は○○%の精度があります」などと正直に申告する企業は信頼できるといえるでしょう。以前、ユビキタスという言葉が流行し定着する前にすたれてしまいました。おそれているのはAIがバブルともいえるほどもてはやされ、その二の舞いになってしまわないか。AIもどきの製品が世の中を席巻し、その反動でAIによる社会変革の芽を摘んでしまう事態です。その間に真のAIが進化し、海外の企業に主導権を握られるシナリオを危惧します。
──働き方も変わりそうです。
野村 人間がAIに使われずに使う側に回り、創造的な仕事をこなすため肝心なことは「なぜ」という疑問を大切にする姿勢です。一例を挙げましょう。日本の製造業の中には、作業工程の工夫を提案しあう改善活動を行っている企業があります。
ある工場の経理担当の女性は、小銭を1枚ずつつまんで枚数を数える作業に常々疑問を抱いていたそうです。彼女はその疑問を持ちつづけていたため、お土産にもらったおせんべいの缶の縦横が10円玉の直径の約10倍あるのに気づきました。改善活動の発表会でスチール缶に10円玉を放り込んでジャラジャラ振って平らに敷き詰め、合計1000円になるのをすばやく計算してみせ、入賞しました。
これまで述べてきたように、AIには多対多のマッチングなどで優れた性能を発揮しますが、直ちに人間に取って替わるだけの能力を有しているわけではありません。作業的な業務から徐々に解放され、より専門的でクリエーティブな働き方が主流になる時代がやってくるのではないでしょうか。
(インタビュー・構成/本誌・小林淳一)